カウンセリング理論~来談者中心アプローチ・精神分析カウンセリング・認知行動療法登場人物~キャリアコンサルタント量産計画

Ⅱ キャリアコンサルティングを行うために必要な知識
目次
カウンセリングに関する理論
この章では、より実践的な理論を紹介します。
実際のキャリアコンサルティングにも活きてくる内容となっているので現場を想定しやすく、覚えやすいと思います。
細目はこちら
1) キャリアコンサルティングの全体の過程において、
カウンセリングの理論及びスキルが果たす役割について詳細な知識を有すること。
2) カウセリングの理論、特徴に関し、次に掲げる事項について一般的な知識を有する こと。
① 代表的なカウンセリング理論の概要(基礎知識)、特徴
・来談者中心アプローチ
・精神分析的カウンセリング
・論理療法
・行動療法
・ゲシュタルト療法
・交流分析
・包括的・折衷的アプローチ
・家族療法
・実存療法
・アサーション 等
② グループを活用したキャリアコンサルティングの意義、有効性、進め方の留意点等
・グループワーク
・グループガイダンス
・グループカウンセリング
・グループエンカウウンター
・サポートグループ 等

多いなぁ

多いけど、結構まとめて覚えられるよ!
あとこの理論は実践的だから覚えやすい!
そもそもカウンセリングとは
さまざまな心理的問題を抱えている人に対して専門的な視点から助言・援助を行うこと。
もともと臨床心理学から発展したものでキャリアコンサルタントのみならず、
医療・福祉・教育などさまざまな分野で実践されています

あくまで助言と援助だからね!
カウンセリング理論にはいろいろありますが、
主に来訪者中心カウンセリング・精神分析的カウンセリング・認知行動カウンセリング(論理療法)のいづれかに分類できます。
主流3つの手法の登場人物から紹介します
登場人物一覧
ロジャーズ(来談者中心アプローチ)
フロイト 精神分析的カウンセリング
ウォルピ・スキナー(行動療法)
エリス・ベック(認知療法)
ロジャーズの来談者中心アプローチ
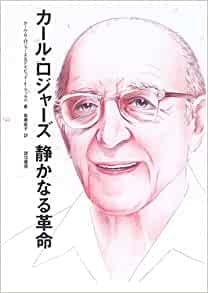

なんて優しそうな微笑み!
この人に相談したい!

すっごい話きいてくれそうでしょ?
来談者中心アプローチ
来談者中心アプローチはその名の通り、相談者の話をよーく聞いて、
相談者が自分自身で問題解決するように仕向けるカウンセリングです。
これは非常に重要です。今のキャリアコンサルタントとはこうあるべきという理論にそっくりです。
非常に実用的で、今でも理論は役に立っています。
重要なのはロジャーズの3原則、エンカウンターグループ、必要かつ十分な6条件です。
ロジャーズの3原則は、
「相手の話を受容して、共感しよう!
そしてカウンセラーもありのままで心理的に安定しよう(自己一致)」
というカウンセラーの基礎の基礎の原則です
エンカウンターグループとは複数人でグループワークを行う集団心理療法のこと。
また必要かつ十分な6条件では治療によってパーソナリティが変化するための条件を上げました。
ロジャーズについて詳しくはこちら
続きましてフロイトです。
フロイトの精神分析的カウンセリング
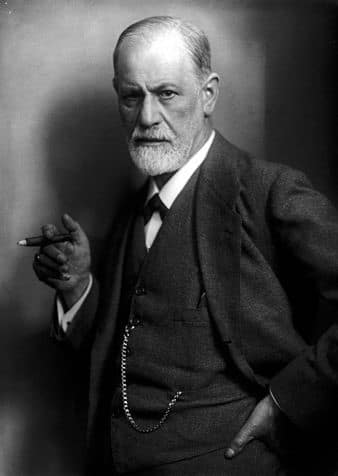
フロイトは名前を聞いたことがあるかもしれません。フロイトは精神分析的カウンセリングを行いました。
フロイトが有名なのはキャリア形成の分野だけでなく、心理学など様々な分野で理論を応用して活用されているから。

いかにも見通されてそうな顔、、、
分析されそう、、、
前にご紹介したエリクソンも精神分析をしていました。フロイトは覚えることが非常に多いです。
エリクソンは精神を分析して精神が発達する過程を描きました。
フロイトは精神を分析して人の無意識に着目しています。無意識的に行動するのにはパターンがあるよね、
キャリコンサルティングをするなら相手の無意識を見逃しちゃいけないよねってことです。
無意識の行動に目を見張りながら、この人はどんな人なんだろうと分析していくカウンセリング手法です。
フロイトについて詳しくはこちら
続いてはウォルピです。
ウォルピの倫理療法・行動療法
その前にちょっと論理療法(認知行動カウンセリング)とは、
・理論に基づいて行動を修正する行動療法
・認知を修正することで症状を改善させる認知療法
を統合したカウンセリング
手法です。
カウンセリング3つの主流
人の話をよく聞こう!来談者中心カウンセリング
人の精神を分析して何を考えているのか暴こう!精神分析カウンセリング
実際の行動や認知を観察して修正しよう!認知行動カウンセリング
普段から行っている自分の行動や思考のクセを整えていくような療法です。
ウォルピは系統的脱感作法という行動療法です。
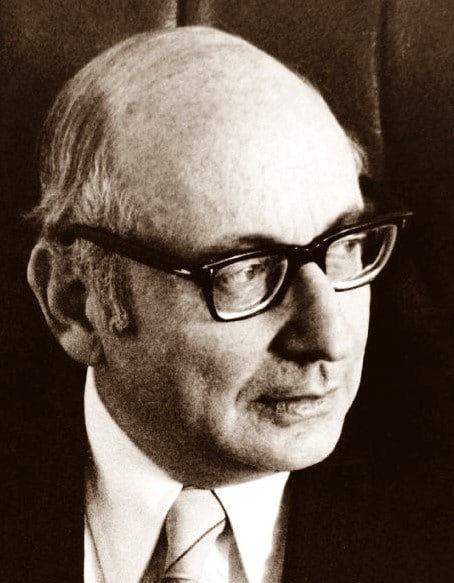

また怖そうなかお、、、

行動を強制する行動療法の2人はどっちも怖そうな顔してるよ、、、
対して認知療法は考え方を変えましょうね!って感じで
優しそうな顔
系統的脱感作法
嫌いなもの、苦手なものをちょっとづつ体験していって克服します。
ニンジンが嫌いな子供にカレーに細切れにしていれて、
次はごろごろのニンジンをカレーに入れて、ハンバーグに添えてみて、
ついにはサラダでだす!みたいな感じです。
行動療法はもう一つあります
スキナーのシェイピング法

それがスキナーのシェイピング法。こちらも行動療法ですが、褒めて伸ばします。
オペラント条件付けというスキナーが開発した考えを基礎としています。
ニンジンを食べさせたいなら、カレーに入った細切れニンジンを食べたら褒める
→ニンジンを食べたら褒められると知った子供はニンジンをもっと食べる
→次はニンジンを大きめにカットして食べたら褒める→、、、、
の繰り返しです。
二人に共通しているのは人の行動を修正しようとしている点です。
行動療法について詳しくはこちら
では認知療法も二人
エリスのイラショナルビリーフ

エリスはイラショナルビリーフという考え方を提唱しました。
イラショナルビリーフとは非論理的な信念です。食べず嫌いなんかもこれですね。
今不安や悩み、いかりは有りますか?
子どもがニンジンを食べなくて悩んでいる。

そもそもニンジンを食べなきゃいけないってなんで思ってるの?
と、悩みなんて他の人から見れば大したことないんです。
考え方を修正すれば悩みはなくなるってのが認知療法です。
もう一人はベック
ベックの自動思考

ベックが考えたのは自動思考です。自動思考とは自分の意志に関係なく自動的に起こる感情のこと。
「ニンジンは食べなきゃいけない」なんて思考は自分の意志とは無関係ですよね?
無意識に当たり前と思っている信念や認知の歪みを修正することで不安を和らげます。
認知療法について詳しくはこちら
というように上記6人がカウンセリング主流の理論を展開しました!
最後におさらいです。
ロジャーズ(来談者中心アプローチ)
フロイト 精神分析的カウンセリング
ウォルピ(行動療法)(系統的脱感作法)
スキナー(行動療法)(オペラント条件付け)
エリス(認知療法)(イラショナルビリーフ)
ベック(認知療法)(自動思考)
この記事の監修者

キャリアコンサルタント
兵庫 直樹
国家資格キャリアコンサルタント。大手外資系ホテル勤務を経て、15年に亘り、マネジメント業務に従事。 その中で人材関連に興味を持ち、キャリアコンサルタントを取得し人材業界へ。その後、持ち前のコミュニケーション能力と資格を生かし、ハローワークにて就業支援に従事してきた異例の経歴!





